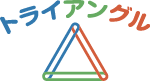【完全ガイド】就労継続支援A型を利用するには?障害福祉サービス受給者証の取得方法を徹底解説
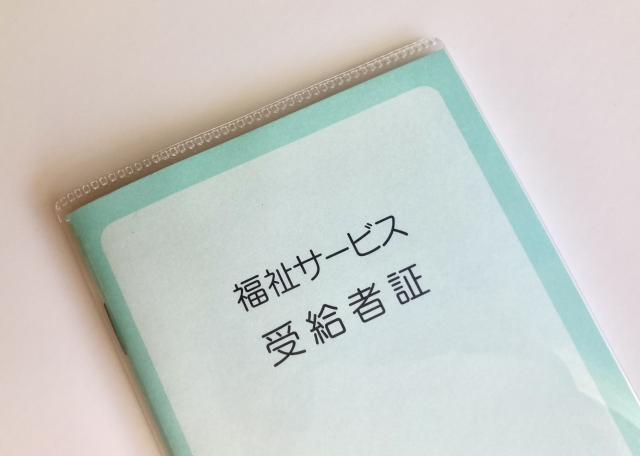

「働きたいという気持ちはあるけれど、体調や心の状態に不安がある…」
「一般企業での就職は難しいけれど、収入を得ながら社会と関わっていきたい」
そんな想いを持つ障害のある方を支えるのが、就労継続支援A型という福祉サービスです。

「A型事業所で働きたいけど、手続きが難しそう…」
「“受給者証”ってよく聞くけど、どうやって手に入れるの?」
──そんな疑問や不安を抱えていませんか?
就労継続支援A型では、障害や難病のある方が事業所と雇用契約を結び、サポートを受けながら安定して働ける仕組みが整っています。
しかし、この制度を利用するには「障害福祉サービス受給者証(以下受給者証)」という証明書が必要です。
この記事では、これからA型事業所の利用を考えている方に向けて
- 受給者証とは何か
- どのような手続きで取得できるのか
- よくある疑問や注意点
などを、初めての方にも分かりやすく解説します。
【目次】
- 就労継続支援A型とは?
- A型事業所の主な特徴
- 自分に合った仕事内容の例
- 「障害福祉サービス受給者証」とは?
- 受給者証が必要な理由
- 受給者証の役割と重要性
- 「障害者手帳」との違い
- 受給者証を取得できる対象者
- 【5ステップ】受給者証の取得方法
- 申請に必要な書類
- 他の就労系サービスとの違い
- 受給者証取得の注意点
- A型事業所利用までの流れ(7ステップ)
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|受給者証はA型利用の第一歩
読み終わるころには、「手続きが不安…」という気持ちがきっと軽くなり、安心して第一歩を踏み出す準備が整うはずです。
就労継続支援A型とは?|まずは制度の概要から

就労継続支援A型(以下A型事業所)は、障害者総合支援法に基づき、障害や難病のある方が雇用契約を結びながら働ける福祉サービスです。
一般企業での就職に不安がある方でも、支援を受けながら安定した就労を目指せます。
主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用形態 | 事業所と雇用契約を結びます(時給制)。※最低賃金が保証されます。 |
| 対象者 | 働く意欲があり、一定の就労能力が認められる障害や難病のある方。 |
| 支援内容 | ・職業訓練(作業指導、スキル習得)・生活支援(体調管理、相談支援)・就労定着支援(一般就労後のフォロー) |
| 目的 | ・将来的な一般就労を目指す・無理のない福祉的就労を継続し、社会参加を図る |
| 利用料 | 原則1割の自己負担あり。※所得や世帯の状況により負担なしになることもあります。 |

このように、A型事業所は「働きたい」という気持ちを尊重し、安心して働ける環境と支援を提供してくれる制度です。
自分に合った仕事を選べる安心感
A型事業所では、体調や障害特性に合わせた配慮がされており、「無理のない範囲で続けられる仕事」が選べます。
ここでは、仕事内容の具体例を分かりやすくご紹介します。

A型事業所の主な仕事内容
| カテゴリ | 仕事内容の例 | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 軽作業系 | ・部品の組み立て ・商品の袋詰め・箱詰め ・シール貼り ・検品・仕分け | 初心者でも取り組みやすく、黙々と作業したい方に向いています。 |
| 清掃・施設管理 | ・施設内の清掃(床・窓・トイレなど) ・ゴミ出しや整理整頓 ・備品の消毒 | 身体を動かす仕事が中心で、ルーチンワークを好む方におすすめ。 |
| 調理・食品加工 | ・弁当やパンの製造補助 ・盛り付け・ラッピング作業 ・食品の検品や梱包 | 手先を使う作業が多く、衛生管理にも気を配る必要があります。 |
| 農作業・園芸 | ・野菜や花の栽培・水やり ・収穫・袋詰め ・畑の整備や草取りなど | 自然の中で作業したい方、適度に身体を動かしたい方に適しています。 |
| PC・IT関連作業 | ・データ入力・文書作成 ・画像加工・チラシ制作 ・ECサイトの商品登録 ・SNS・ブログ投稿補助 ・簡単な動画編集 | 座って作業できるため体力に不安がある方におすすめ。 スキル次第で一般就労の可能性も広がります。 |
「体を動かすのが好き」「黙々と作業したい」「PCを使った仕事に挑戦してみたい」など、一人ひとりの得意や希望に応じた仕事選びができるのがA型事業所の魅力です。

仕事内容は事業所によって異なりますので、見学や体験などで確認しておきましょう。
📝関連記事はこちらから
就労継続支援A型とは?対象・仕事内容・利用方法・選び方まで完全解説【2025年版】
【誰が利用できる?】就労継続支援A型の対象者とその条件を徹底解説
A型事業所の利用に必須!「障害福祉サービス受給者証」とは?
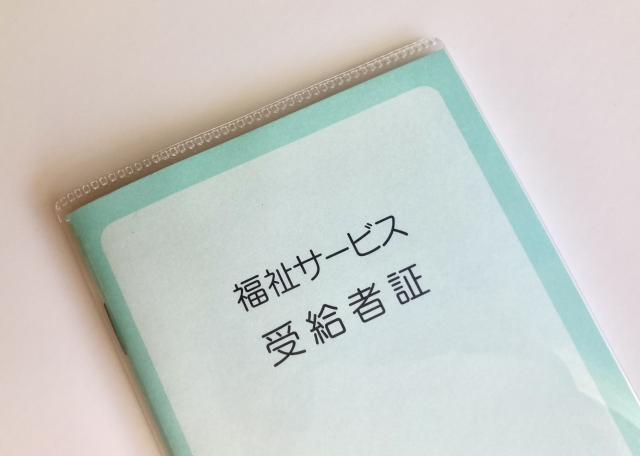
障害福祉サービス受給者証とは、障害のある方がA型事業所をはじめとする各種福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される「公的な利用許可証」のことです。
この受給者証があることで、あなたは「この福祉サービスを利用することが適切である」と行政に認められたことになり、国や自治体からの費用補助を受けながらサービスを利用できます。
なぜ必要なの?

A型事業所は公的サービスの一環として提供されるため、行政からの利用許可=受給者証が必須となります。
事業所は、この受給者証に基づいて契約を結び、国や自治体から報酬を受け取る仕組みです。
安心して福祉サービスを受けるために必要な大切な証明書なのです。
受給者証の役割と重要性

受給者証は、単なるカードや書類ではありません。
以下の主に3つの重要な役割を担っています。
①サービスの利用資格を証明する
A型事業所は、受給者証を持つ人に対してサービスを提供する義務があります。
これがなければ、事業所側もあなたを正式な利用者として受け入れることができません。
②適切なサービス内容を決定する
受給者証には、あなたが利用できるサービスの種類(例:就労継続支援A型)、1ヶ月に利用できる日数(支給量)、有効期間などが明記されています。
これにより、あなたに合った適切な支援が計画的に提供されます。
③利用者負担額を決定する
福祉サービスの利用には費用がかかりますが、その全額を自己負担するわけではありません。
受給者証には、前年の世帯所得に応じた「利用者負担上限月額」が記載されており、どれだけサービスを利用しても、その上限額以上を支払う必要はありません。

このように、受給者証は障害のある方が福祉サービスを安心・適切に利用するための大切な役割を担う証明書です。
「障害者手帳」とは何が違うの?

よく混同されがちなのが「障害者手帳」です。
この2つは役割が全く異なります。
| 障害福祉サービス受給者証 | 障害者手帳 | |
| 役割 | 福祉サービスの利用を許可するもの | 障害があることを証明するもの |
| 目的 | 就労支援や生活介護などのサービスを受けるため | 税金の控除や公共料金の割引などを受けるため |
| 発行元 | 市区町村の障害福祉担当部署 | 都道府県・指定都市・中核市 |
簡単に言うと

「障害者手帳」が身分証明書のようなもの、「受給者証」が特定のサービスを受けるためのチケットのようなものだと考えると分かりやすいでしょう。
受給者証は誰がもらえるの?対象となる方

具体的には、原則として18歳以上の方で以下の条件に当てはまる方が対象です。
障害の種類による対象者
- 身体障害がある方: 身体機能に何らかの障害がある方(視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など)
- 知的障害がある方: 知的機能の障害により、日常生活に支障がある方。
- 精神障害がある方: 統合失調症、うつ病、双極性障害などの精神疾患がある方。
発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)も法律上、精神障害に含まれます。
- 難病患者: 障害者総合支援法で定められた特定の難病(治療法が確立していない疾病など)により、一定の障害があると認められる方。
就労や生活支援が必要な方
就労継続支援A型やB型、就労移行支援、生活介護、居宅介護などの障害福祉サービスを利用して、自立した生活や社会参加を目指す方。
その他重要なポイント💡

障害者手帳がなくても、医師の診断書などで障害や支援の必要性が認められれば、受給者証を申請できる場合があります。
手帳は必須ではないので、まずはお住まいの市区町村に相談してみましょう。
【5ステップで解説】受給者証の申請から取得までの全流れ

「手続きが難しそう…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、全体の流れを知っておけば心配はいりません。
ここでは、相談から受給者証の交付までを5つのステップに分けて、わかりやすくご紹介します。
- STEP 1: まずは相談窓口へ行こう
お住まいの市区町村の「障害福祉課(名称は自治体により異なります)」や、「相談支援事業所」が最初の相談窓口になります。
この段階で、「A型事業所で働きたいと考えている」という希望を伝え、今後の手続きについて、具体的なアドバイスをもらいましょう。

- STEP 2: サービスの利用申請を行う
申請書、障害者手帳や診断書、マイナンバーがわかるものなどが必要です。
相談窓口で案内された必要書類を準備し、市区町村の障害福祉窓口で正式に申請手続きを行います。

- STEP 3: 認定調査(ヒアリング)を受ける
日常生活の状況や心身の状態、サービス利用の希望などについて、市区町村の担当者や認定調査員から聞き取り(ヒアリング)が行われます。

- STEP 4: 「サービス等利用計画案」を作成・提出する
相談支援専門員と一緒に、希望するサービス内容に応じた「計画案」を作成します。
「どのような目標を持ち、そのためにどんな福祉サービスを、どのくらいの頻度で利用したいか」を具体的にまとめた、支援計画書のことです。

- STEP 5: 支給決定と受給者証の交付
申請から交付まで、一般的に1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
提出された申請書類、認定調査の結果、サービス等利用計画案などを基に、市区町村が総合的に審査を行います。
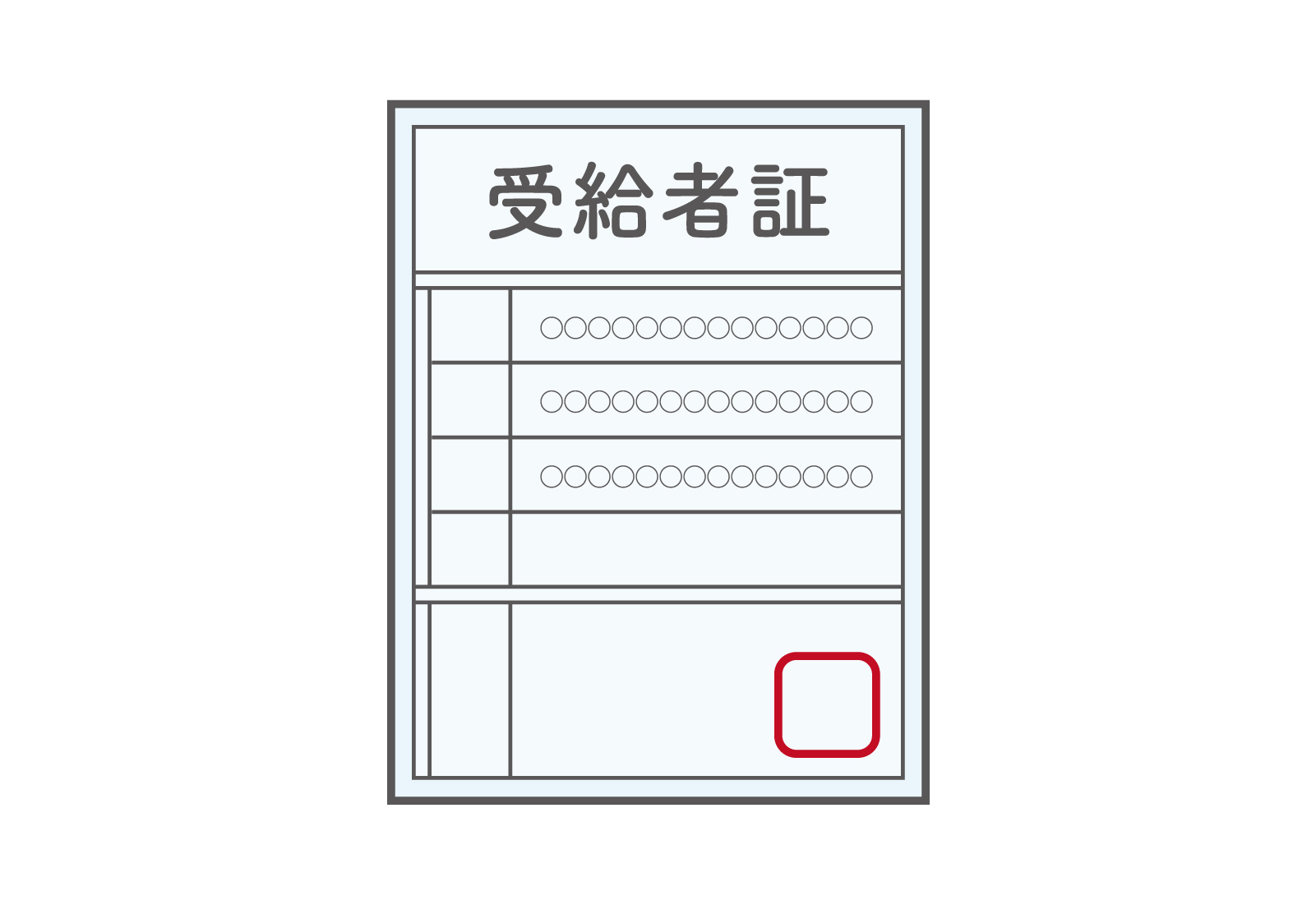
- STEP 6:A型事業所との契約・利用開始
受給者証を持って、希望するA型事業所と正式に雇用契約を締結。実際の利用がスタートします。
受給者証が手元に届いたら、いよいよA型事業所との利用契約が可能になります。

届いた受給者証は内容を必ず確認し、大切に保管してください。
また、受給者証には有効期間が定められていますので、期限が近づいたら更新手続きが必要になることも覚えておきましょう。
申請に必要な書類
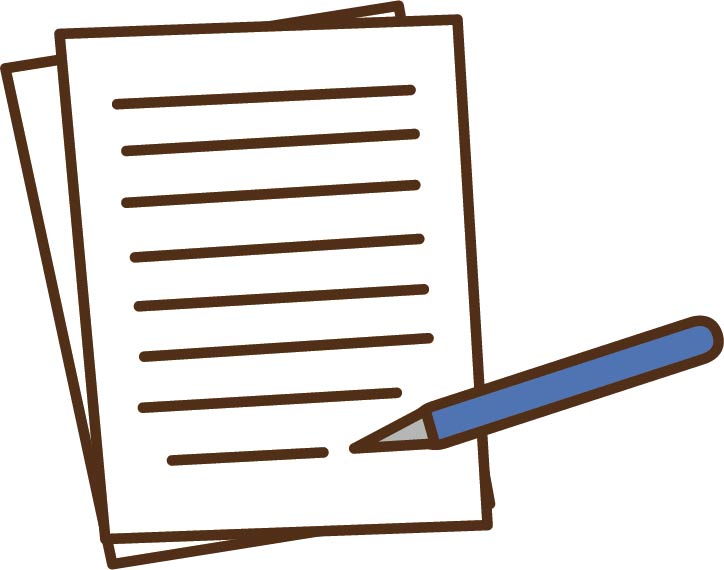
障害福祉サービス受給者証の申請に必要な主な書類は以下の通りです:
必要な主な種類
- 支給申請書:市区町村の窓口で受け取ります
- 障害の状況を示す書類:障害者手帳、医師の診断書・意見書など
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
- 印鑑:認印でOKな場合がほとんどです
- 所得確認書類:課税証明書など(自己負担上限額の決定に必要)
申請時は、お住まいの自治体によって異なる場合があるため、事前に確認するのがおすすめです。
他の就労サービスとの違い

受給者証で利用できる就労系サービスには、A型事業所の他に「B型事業所」や「就労移行支援」もあります。
それぞれの違いを理解しておくと、自分に最適なサービスを選びやすくなります。
| サービス種別 | 就労継続支援A型事業所 | 就労継続支援B型事業所 | 就労移行支援 |
| 雇用契約 | あり | なし | なし |
| 給料/工賃 | 給料(最低賃金以上) | 工賃(生産活動の対価) | 基本的になし |
| 目的 | 支援を受けながら働く | 自分のペースで働く訓練 | 一般企業への就職準備 |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし | 原則2年間 |
受給者証を申請する際には、どのサービスを利用したいかを明確に伝えることが重要です。
✅ 障害福祉サービス受給者証の注意点

障害福祉サービス受給者証を申請・取得する際には、事前に知って、おくべき注意点があります。
手続きをスムーズに進めるために、よくあるポイントを確認しましょう。
- 申請から交付までに1~2か月かかる
利用開始希望日がある場合は、早めの申請が必要です。
- 有効期限がある
多くの場合、1年ごとの更新が必要です。
期限切れに注意しましょう。 - 有効期限が切れてしまうと、事業所が支援できなくなる可能性もあるため、更新時期はカレンダー等でしっかり管理しましょう。
- 支給決定は自治体の審査による
申請しても、必ずしも希望通りのサービスが受けられるとは限りません。
- 所得によって利用者負担額が異なる
世帯の課税状況により、月ごとの上限額が設定されます。
- 内容に変更があった場合は必ず届出を
住所変更、サービスの追加・中止、収入状況の変化などがあれば速やかに自治体へ届け出ましょう。 - A型からB型への変更、通所日数の変更などがある場合も、再度計画案や申請が求められることがあります。
- 障害者手帳がなくても申請可能な場合がある
医師の診断書や意見書等で代用できることがありますが、事前確認が必要です。

以上の点を押さえておけば、受給者証の申請も安心して進められます。
わからないことがあれば、早めに相談機関に問い合わせることをおすすめします。
📝参考(外部)リンク
障害福祉サービス受給者証とは?障害者手帳との違いや取得の流れを紹介: 株式会社Kaien
📝関連記事はこちらから
就労継続支援B型を活用するために知っておきたい「障害福祉サービス受給者証」とは?
A型事業所の利用までの主な流れ

A型事業所を「利用してみたい」と思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、利用開始までの基本的な流れを7つのステップで解説します。
- ①情報収集・相談
お住まいの市区町村の障害福祉課や障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所で制度の説明を受け、自分に合った事業所を探します。

- ②事業所の見学・体験
気になるA型事業所を見学したり、体験利用を通じて、実際の職場環境や仕事内容を自分の目で確かめてみましょう。

- ③面接・適性確認
事業所で面接を受け、働く意欲や体調、適性などを確認します。
面接に合格すれば次のステップに進みます。

- ④障害福祉サービス受給者証の申請
面接通過後、障害者手帳や医師の診断書を用意し、市区町村の福祉課などに障害福祉サービス受給者証の申請を行います。
審査の後、受給者証が発行されます。
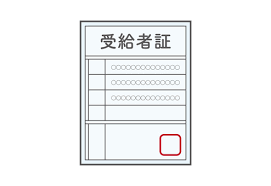
- ⑤雇用契約を結ぶ
受給者証の取得後、正式に事業所と雇用契約を結びます。契約内容や勤務条件について説明を受け、納得した上で契約を進めます。

- ⑥個別支援計画の作成
支援員と相談しながら、働き方や支援内容を具体的に計画した個別支援計画を作成します。

- ⑦利用開始
支援を受けながら実際に就労を開始します。
定期的に面談や計画の見直しを行いながら、働きやすい環境づくりを進めます。

まずは事業所やお住まいの地域の相談窓口での相談をしましょう。
ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要となります。
この流れは一般的なもので、自治体や事業所によって多少異なる場合があります。
よくある質問(FAQ)
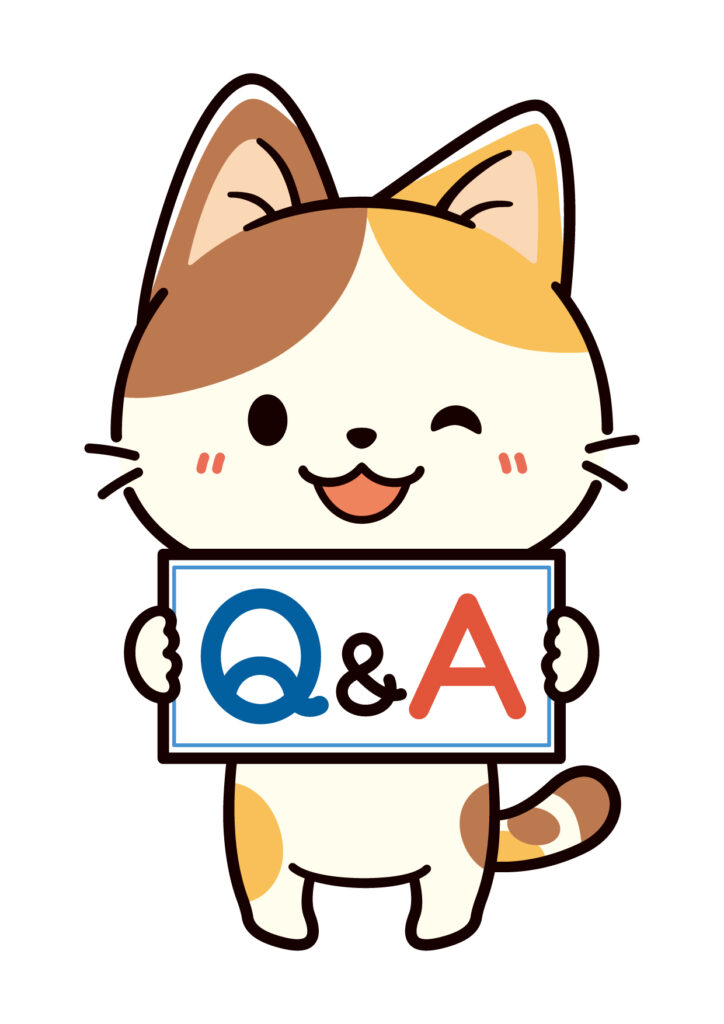
最後に、受給者証の申請に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
-
障害者手帳がないと受給者証は申請できませんか?
-
必ずしも必須ではありません。
医師の診断書や意見書があれば、障害の状況やサービスの必要性が認められ、申請が可能な場合があります。
ただし、自治体によって判断が異なるため、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。
-
受給者証の申請に費用はかかりますか?
-
受給者証の申請手続き自体に費用はかかりません。無料で申請できます。
ただし、必要書類として医師の診断書を取得する場合、その発行手数料は自己負担となります。
-
受給者証があれば、どこのA型事業所でも利用できますか?
-
受給者証に「就労継続支援A型」の支給が決定されていれば、全国どのA型事業所でも原理的には利用可能です。
-
受給者証の申請は本人以外でもできますか?
-
はい、ご家族や支援者(後見人、保佐人、相談支援専門員など)が代理で申請手続きを行うことも可能です。
-
受給者証を紛失してしまったらどうすればいいですか?
-
すぐにお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に連絡し、再発行の手続きを行ってください。身分証明書などを持参すれば、その場で再発行してもらえる場合が多いです。
まとめ|「障害福祉サービス受給者証」はA型事業所利用の第一歩

就労継続支援A型は、障害がある方が安心して働き、スキルアップや社会参加を目指すための大切な制度です。
そして、その入り口となるのが「障害福祉サービス受給者証」です。
取得には多少の手続きが必要ですが、支援者と連携すればスムーズに進めることが可能です。
あなたの「働きたい」という気持ちを形にするために、まずは一歩踏み出してみませんか?
📝参考(外部)リンク
就労継続支援A型事業所(全国版)|LITALICO仕事ナビ
就労継続支援A型事業所(京都市)|はたらきまひょ
🌈“やってみたい!”を応援する場所、トライアングルへようこそ!

💡「トライアングル」ってどんなところ?
名前に込めた想い──
「トライ(Try)=挑戦」
「アングル(Angle)=見方を変える」

そして「トライアングル」が大切にしている三つの視点:
利用者さん × スタッフ × 地域社会
この“バランスの三角形”が、私たちの出発点です。
🌱“作業”ではなく、“成長”を育む場所
私たちトライアングルグループは、京都市伏見区の藤森と竹田にて、就労継続支援A型事業所を運営しています。
(※竹田事業所はA型・B型の併設事業所です)

✨あなたの「できるかも」が「できた!」に変わる
✨あなたの「好き」や「得意」を一緒に見つける
✨あなたの「挑戦したい」を何度でも応援する
そんな“自分らしく働く”ことを目指す場所です。
💪不安があっても大丈夫。あなたのペースでOK!

「やってみたいけど不安…」
「うまくいかなかったらどうしよう…」
そんな気持ち、私たちはよくわかります。
だからこそ、失敗を恐れず挑戦できる“安心できる環境”を整えました。
🛠幅広いお仕事と支援体制
あなたの“やってみたい”に合わせて、さまざまな業務をご用意!
- 軽作業
- 創作・クラフト活動
- パソコン作業(SNS代行・ブログ作成・デザイン・動画編集など幅広い作業を提供)
- 在宅ワークも対応可能!
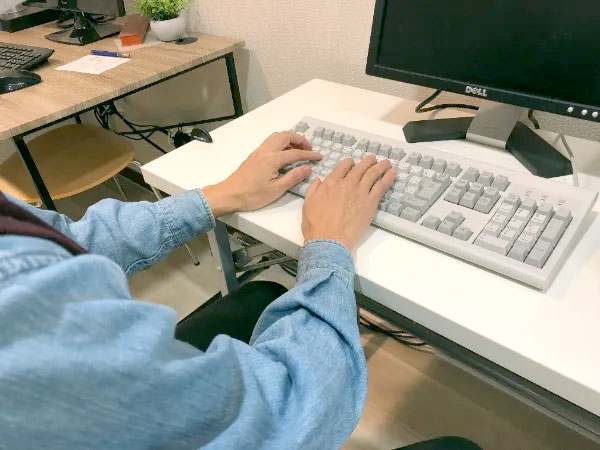
▶詳しくはこちらの「仕事の内容」もご覧ください。
就労に不安がある方も、ブランクがある方も、「挑戦したい」という気持ちがあれば、それだけで充分です。
さらに
📘資格取得支援
💼就職サポート
💬定期面談・個別相談
など、安心のサポート体制も充実!
💬まずは見学・体験からでもOK!
「ちょっと気になる」
「話だけでも聞いてみたい」
そんな方も、見学・体験を随時受付中!
あなたの“はじめの一歩”を、スタッフ一同あたたかくお迎えします。
✨あなたの未来、一緒に描いてみませんか?
「やってみたい」「挑戦してみたい」
——その前向きな気持ちこそが、すべてのはじまりです
あなたが思い描く「なりたい自分」を実現するために、トライアングルは全力で応援します。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
🏢事業所のご案内
🔹トライアングル藤森(就労継続支援A型事業所)

〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町840 セントラルプラザ1階
📞075-644-4123
🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)
アクセス:
🚶京阪本線「藤森駅」 徒歩5分
🚶JR奈良線「JR藤森駅」 徒歩20分
🚌市バス「藤ノ森」停留所 徒歩2分
🔹トライアングル竹田(就労継続支援A型・B型事業所)

〒612-8446
京都市伏見区竹田中内畑町2番地 堀田ビル3階
📞070-3272-4349
🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)
アクセス:
🚶近鉄・地下鉄「竹田駅」 徒歩8分
🚌市バス「竹田内畑町」停留所 徒歩1分
各事業所へのアクセスは「アクセス情報」をご覧ください。