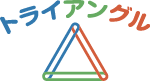障害者手帳を持って就労継続支援A型を利用するメリット|知らないと損する5つのポイント
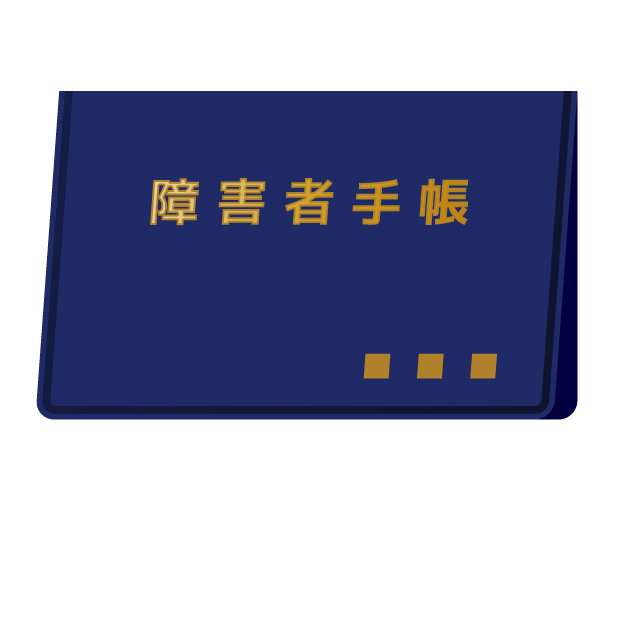

「一般企業で働くのは少し不安…でも、安定した収入を得ながら働きたい」
「就労継続支援A型に興味があるけど、利用するには障害者手帳が絶対に必要?」
「障害者手帳を持っていると、どんな良いことがあるんだろう?」
障害や難病があっても自分らしい働き方を探している方にとって、就労継続支援A型事業所は、雇用契約を結び、安定した給料を得ながらスキルアップを目指せる心強い選択肢です。
しかし、利用を検討する上で「障害者手帳の有無」について疑問や不安を感じる方は少なくありません。
本記事では、就労継続支援A型の利用における障害者手帳の役割やメリット、そして手帳がない場合の利用方法まで、あなたの疑問を一つひとつ丁寧に解説します。
この記事を読めば、安心して次の一歩を踏み出すための知識が身につきます。
📑目次
- はじめに|就労継続支援A型とは?
- A型事業所の基本と特徴
- 誰が利用できる?対象者の条件
- A型事業所でできる仕事の種類
- A型事業所の利用に障害者手帳は必要?
- 障害者手帳を持つ5つのメリット
- 手帳なしの場合に知っておきたいデメリット
- 障害者手帳の申請方法|5ステップ
- 手帳がない場合の利用方法
- 障害者手帳を利用する際の注意ポイント
- 【体験談】利用者のリアルな声
- A型事業所を利用するまでの流れ|7ステップ
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|無理なく一歩を踏み出そう
そもそも就労継続支援A型事業所ってどんなところ?

まずは基本からおさらいしましょう。
就労継続支援A型(以下A型事業所)がどのような場所なのかを理解することが、自分に合った選択をするための第一歩です。
A型事業所とは、障害や難病のある方が、事業者と雇用契約を結んだ上で、支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。
一般企業への就職が困難な方が対象で、一定の支援がある環境で働きながら、知識や能力の向上を目指します。
最大の特徴は「雇用契約を結ぶ」点にあり、これにより労働者として法律で定められた最低賃金以上の給料が保証されます。
就労継続支援A型事業所(以下A型事業所)は、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。
一般企業での就労が難しい方に対して、働く場と必要なサポートを提供し、将来的な一般就労を目指すことも可能です。
A型事業所の目的と役割
A型事業所の主な目的は、以下の通りです。
- 雇用契約を結ぶ: 利用者と事業所が雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。
- 働く機会の提供: 利用者の能力や適性に応じた仕事を提供します。
- スキルアップ支援: 職業訓練やビジネススキルの向上をサポートします。
- 一般就労への移行支援: 企業への就職活動をサポートし、定着支援も行います。
対象となる方
- 原則として18歳以上65歳未満の方
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病をお持ちの方
- 一般企業への就職が困難な方で、A型事業所での就労を通じて一般就労を目指したいという意欲のある方
📝関連記事はこちらから
就労継続支援A型とは?対象・仕事内容・利用方法・選び方まで完全解説【2025年版】
【誰が利用できる?】就労継続支援A型の対象者とその条件を徹底解説
就労継続支援A型の雇用契約完全ガイド|初心者が知っておくべき給料・条件・注意点
A型事業所はどんな人が利用できる?|対象者や仕事内容をわかりやすく解説

A型事業所について、もう少し詳しく見ていきましょう。
A型事業所を利用できる人には、いくつかの条件があります。
ここでは具体的に、どんな人が対象になるのか、そしてどんな仕事ができるのかをわかりやすくご紹介します。
対象者
主な対象者
- 原則18歳以上65歳未満の方
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病などがある方
- 企業等に就労することが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる方
これらの条件に当てはまるか不安な方は、まずは市区町村の窓口や事業所に相談してみるのがおすすめです。
仕事内容
A型事業所では事業所によってさまざまな仕事があります。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| PC作業 | データ入力、文書作成、Webサイト更新、文字起こし |
| 事務作業 | 書類整理、封入作業、名刺やチラシの作成補助 |
| 軽作業 | 部品の組み立て、検品、袋詰め、シール貼り、ピッキング |
| サービス業関連 | カフェ・レストランの調理補助、ホールスタッフ、清掃、販売接客 |
| クリエイティブ系(IT関連) | デザイン制作、イラスト作成、動画編集、SNS運用 |
| 農業・食品加工 | 野菜や花の栽培、農作物の収穫、パンやお菓子の製造・包装 |

A型事業所では、多様な仕事の中から自分に合った作業を選び、無理なく働くことができます。
まずは気になる事業所を見学し、仕事内容や環境を確認してみましょう。

当事業所トライアングルでは、SNS代行を専門としており、ブログ作成、Instagram、TikTok、YouTubeの動画編集、デザインなどの業務を行っております。こちらの「仕事の内容」ページもご覧ください。
A型事業所の利用に障害者手帳は必須?

ここからが本題です。
多くの方が気になる「障害者手帳の必要性」について解説します。
結論から言うと、就労継続支援A型の利用に障害者手帳は必ずしも必須ではありません。
障害者総合支援法上の対象者には「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、または難病のある方」と定められており、手帳の所持は必須条件とされていないのです。
ただし、障害者手帳を所持している方が、利用申請の手続きがスムーズに進むことは事実です。
手帳は、障害があることを客観的に証明する公的な書類だからです。
そのため、多くの自治体や事業所では、手帳の所持を推奨している場合があります。
障害者手帳を持ってA型事業所を利用する5つのメリット

では、障害者手帳を持っていると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは主な5つのメリットをご紹介します。
メリット1:利用手続きがスムーズに進む
A型事業所を利用するには、お住まいの市区町村か「障害福祉サービス受給者証」を交付してもらう必要があります。
障害者手帳があれば、障害の状況を客観的に証明できるため、この受給者証の申請手続きが非常に円滑に進みます。

障害福祉サービス受給者証とは・・
障害のある方が就労継続支援A型やB型、居宅介護、生活介護などの障害福祉サービスを利用するために必要な証明書です。
市区町村から交付される正式な書類で、これがないと多くの福祉サービスを利用することができません。
メリット2:利用できる事業所の選択肢が広がる
事業所によっては、支援の専門性などから特定の障害種別の方を主な対象としている場合があります。
障害者手帳で障害種別が明確になっていれば、自分の特性に合った事業所を見つけやすくなります。
また、手帳保持者を優先的に受け入れている事業所も存在します。
メリット3:受けられる配慮やサポート内容が明確になる
手帳には障害の等級や特性に関する情報が記載されています。
事業所側は、その情報を基に、あなたに必要な配慮(例:業務量の調整、定期的な面談、休憩の取り方など)を盛り込んだ「個別支援計画」を立てやすくなります。
これにより、ミスマッチを防ぎ、安心して働き始めることができます。
メリット4:将来の一般就労(障害者雇用枠)に有利になる
A型事業所での経験を活かして、将来的に一般企業の障害者雇用枠での就職を目指す方も多くおられます。
その際、障害者手帳は応募の必須条件となるケースがほとんどのため、A型事業所にいるうちから、一般就労を見据えた準備ができます。
メリット5:生活全般の経済的サポート
障害者手帳を持っていると、就労継続支援A型の利用だけでなく、日常生活でもさまざまな経済的メリットがあります。
例えば、以下のような支援が受けられます。
主な支援
- 公共交通機関の運賃割引
電車・バスなどの料金が割引され、通勤や通院の負担を減らせます。 - 公共施設の入場料割引・免除
美術館や博物館、公営プールなどの施設が無料または割引で利用できます。 - 税金の控除
所得税や住民税で「障害者控除」が適用され、税負担を軽くできます。 - 携帯電話料金の割引
一部の携帯キャリアでは、障害者手帳を提示すると割引プランが利用できます。
これらの制度を活用することで、毎月の固定費を抑えられ、安定した生活を送りやすくなるのが大きなメリットです。
就労継続支援A型の安定収入と合わせて、生活全体の安心につながります。
障害者手帳なしだとどうなる?知っておきたい5つの注意点

障害者手帳がなくても就労継続支援A型は利用できますが、手帳を取得しないことで不便になることもあります。
ここでは、手帳を持たない場合に知っておきたい注意点をまとめました。
1. 利用できる支援や制度が限られる
障害者手帳がないと、公共交通機関の運賃割引や税金の控除、医療費助成などの公的な支援が受けられない場合があります。
日常の負担を減らす制度が使えないのは、経済面で大きな差につながることもあります。
2.A型事業所の利用申請がスムーズに進みにくい
手帳がない場合、医師の診断書など追加の証明書類が必要です。
自治体によっては書類の準備や審査に時間がかかることがあり、利用開始までに時間がかかることもあります。
3. 自分の障害種別や等級が客観的に示せない
手帳には障害の種別や程度が記載されています。
事業所が必要な配慮や個別支援計画を立てる際の参考になるため、手帳がないと情報が不足し、支援内容が合わない場合があります。
4. 将来の障害者雇用枠での就職で不利になる場合がある
一般企業の「障害者雇用枠」で就職を目指す場合、多くの企業では障害者手帳の提示が必要です。
手帳がないと障害者枠での応募ができず、選択肢が狭まる可能性があります。
5.将来の申請で手間が増えることも
後から手帳を申請する場合、診断書の取得や審査に時間がかかるほか、状況によってはすぐに認定されないこともあります。
早めに準備しておく方が安心です。
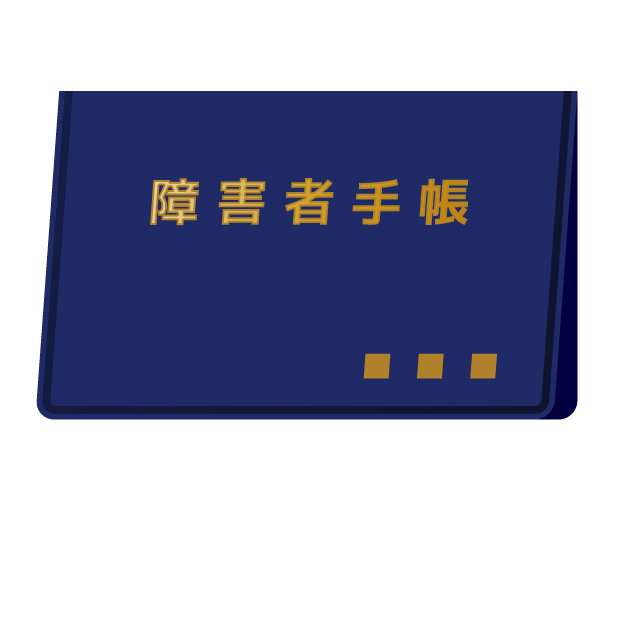
障害者手帳がなくてもA型事業所を利用することは可能ですが、将来の選択肢や受けられる支援を考えると、取得を検討しておくのがおすすめです。
不安な場合は、お住まいの市区町村の福祉課や相談支援員に気軽に相談してみましょう。
📝関連記事はこちらから
【完全保存版】障害者手帳で利用できるサービス一覧|知らなきゃ損する活用法
障害者手帳の申請方法

障害者手帳を取得することで、さまざまな支援やサービスを受けやすくなります。
ここでは、申請の基本的な流れをわかりやすく5つのステップでご紹介します。
- ①市区町村の福祉課に相談する
- まずはお住まいの市役所・区役所などの福祉窓口に相談しましょう。

- ②必要な書類を用意する
- ・医師の診断書(指定様式)
・申請書(窓口で配布)
・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
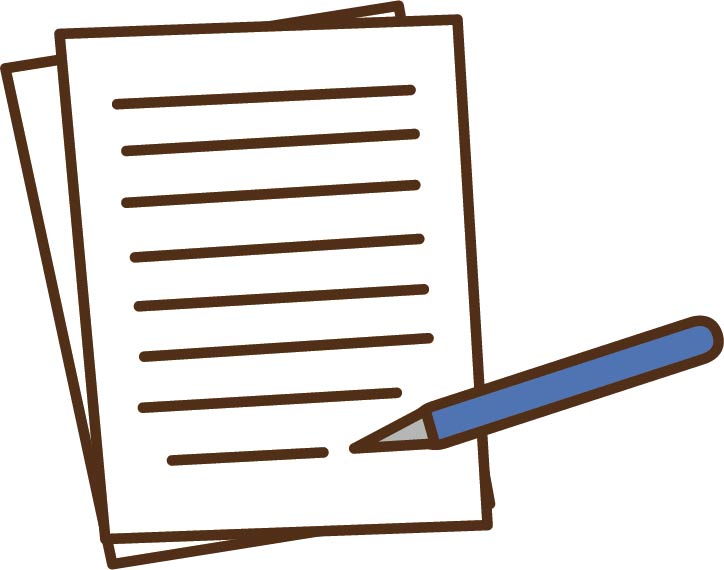
- ③申請書類を提出する
- 必要書類をそろえたら、福祉課の窓口に提出します。

- ④審査・判定を受ける
- 提出後、役所や専門機関で障害の程度について審査が行われます。

- ⑤結果通知・手帳の交付
- 審査結果が出ると、認定された場合は障害者手帳が交付されます。

障害者手帳がなくてもA型事業所を利用できるケースとは?

手帳が必須ではないとはいえ、「手帳がない場合はどうすればいいの?」と不安に思う方もいるでしょう。ご安心ください。
手帳がない場合でも、以下の方法でA型事業所の利用対象者であることを証明できます。
ケースその①医師の診断書や意見書で代用する
障害者手帳の代わりに、医師が発行した「診断書」や「意見書」で申請が可能です。
どの医療機関のどんな書類が必要になるかは、市区町村の窓口で確認しましょう。
この書類には、障害や疾病の状態、就労に関する医師の所見などが記載されます。
ケースその②自立支援医療受給者証(精神通院医療)などを提示する
精神疾患により通院している場合、「自立支援医療受給者証」が手帳の代わりとして認められることがあります。
これも障害の状況を証明する公的な書類の一つです。
自立支援医療受給者証
精神疾患などの治療や通院にかかる医療費の自己負担を軽減するために交付される証明書です。
正式には「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」と呼ばれることが多いです。

まずは市区町村の障害福祉窓口へ相談しましょう!
手帳の有無にかかわらず、最初のステップは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談することです。
専門の相談員が、あなたの状況をヒアリングし、必要な手続きや書類について具体的にアドバイスしてくれます。
📝関連記事はこちらから
【併用OK】就労継続支援A型と自立支援医療|メリットと手続き、活用のポイントを徹底解説
障害者手帳を取得・利用する際の注意ポイント

障害者手帳はさまざまな支援を受けるために役立ちますが、正しく取得し活用するためにはいくつか注意すべきポイントがあります。
- 申請には医師の診断書が必要
正確な診断が重要なので、かかりつけ医に相談しましょう。
- 自治体ごとに申請方法や必要書類が異なる場合がある
お住まいの市区町村の窓口で事前確認をすることが大切です。
- 手帳の有効期限や更新時期を忘れない
期限切れになる前に、早めに更新手続きを行いましょう。
- 障害の程度や内容に応じて手帳の等級が決まる
自分の状況に合った等級が付くため、不明点は専門家に相談すると安心です。
- 手帳の紛失・破損に注意
再発行手続きが必要になるため、大切に保管しましょう。
- 手帳の提示は必要な時だけに
個人情報保護の観点から、提示が求められる場合以外は無理に見せる必要はありません。
- 手帳を持っていてもサービス利用に事前手続きが必要な場合がある
利用したい支援やサービスの条件を事前に確認しましょう。
障害者手帳を上手に活用することで、日常生活や就労の支援につながります。
疑問や不安があれば、専門窓口に相談して安心して利用しましょう。
実際にA型事業所を利用している方の声

実際にA型事業所を利用している方々の声をご紹介します。
- Aさん(20代・発達障害)
「一般企業で働いていた頃は人間関係がうまくいかず、体調を崩してしまいました。A型事業所では支援員さんが相談に乗ってくれて、無理のないペースで働けます。給与も安定しているので、生活の見通しが立てやすくなりました。」
- Bさん(40代・精神障害)
「障害者手帳を取得してから、医療費助成や公共交通機関の割引が受けられるようになり、
通院や通勤の負担が減りました。A型事業所では毎月の給与があるので、経済的にも安心です。」
- Cさん(30代・手帳なし・うつ病)
「当初は障害者手帳を持っていなかったのですが、主治医の診断書を提出してA型事業所を利用できました。手帳がなくても支援員さんがしっかりサポートしてくれて、無理なく働きながら少しずつ自信を取り戻しています。
このように、A型事業所は一人ひとりに合った働き方を支え、安心して仕事を続けられる場所です。
自分らしく、無理なく働く一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
A型事業所を利用するまでの流れ - 安心の7ステップ

「利用してみたい」と思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、利用開始までの基本的な流れを7つのステップで解説します。
- ①情報収集・相談
お住まいの市区町村の障害福祉課や障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所で制度の説明を受け、自分に合った事業所を探します。

- ②事業所の見学・体験
気になるA型事業所を見学したり、体験利用を通じて、実際の職場環境や仕事内容を自分の目で確かめてみましょう。
📝関関連記事はこちらから
【失敗しない】就労継続支援A型事業所の選び方|自分に合った職場を見つける8つのポイント

- ③面接・適性確認
事業所で面接を受け、働く意欲や体調、適性などを確認します。
面接に合格すれば次のステップに進みます。

- ④障害福祉サービス受給者証の申請
面接通過後、障害者手帳や医師の診断書を用意し、市区町村の福祉課などに障害福祉サービス受給者証の申請を行います。
審査の後、受給者証が発行されます。
📝関連記事はこちらから
【完全ガイド】就労継続支援A型を利用するには?障害福祉サービス受給者証の取得方法と注意点を徹底解説!
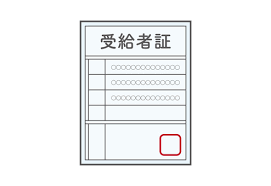
- ⑤雇用契約を結ぶ
受給者証の取得後、正式に事業所と雇用契約を結びます。契約内容や勤務条件について説明を受け、納得した上で契約を進めます。

- ⑥個別支援計画の作成
支援員と相談しながら、働き方や支援内容を具体的に計画した個別支援計画を作成します。

- ⑦利用開始
支援を受けながら実際に就労を開始します。
定期的に面談や計画の見直しを行いながら、働きやすい環境づくりを進めます。

まずは事業所やお住まいの地域の相談窓口での相談をしましょう。
ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要となります。
この流れは一般的なもので、自治体や事業所によって多少異なる場合があります。
わからないことがあれば、支援員や相談支援専門員に遠慮なく相談しながら、一歩ずつ進めていきましょう。
よくある質問(FAQ)
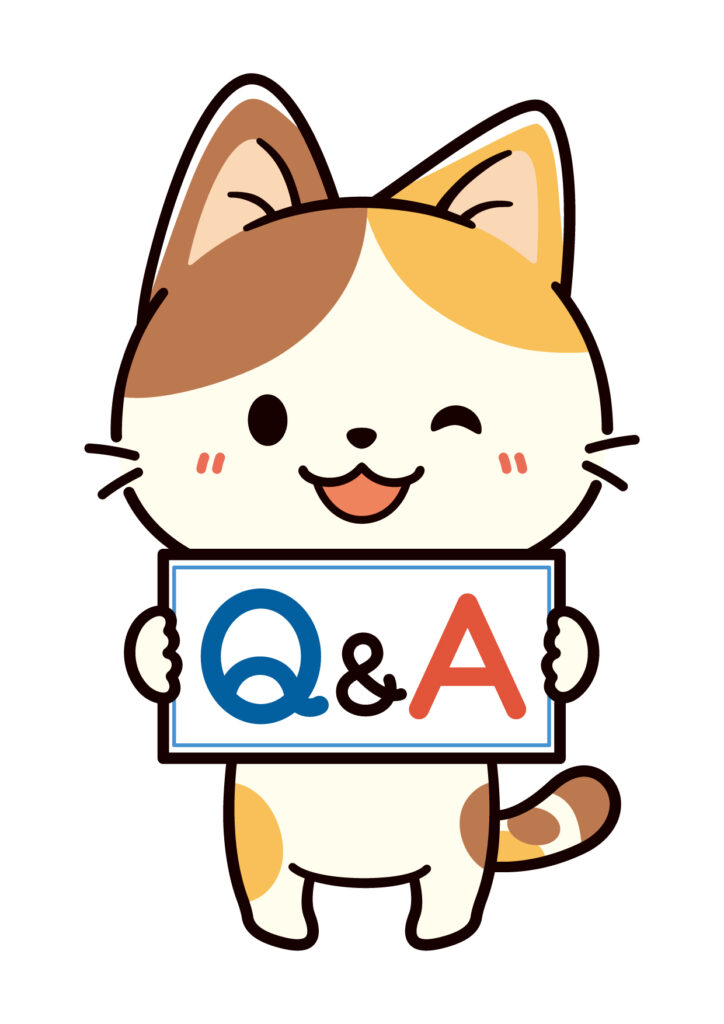
最後に、A型事業所や障害者手帳に関するよくある質問にお答えします。
-
A型事業所から一般企業への就職は可能ですか?
-
はい、可能です。A型事業所の目的の一つは、利用者がスキルや自信をつけ、最終的に一般企業へ就職(一般就労)することです。多くの事業所では、履歴書の書き方や面接練習など、就職活動のサポートも行っています。
-
手帳がなくても利用できる場合、利用時のサポートに違いはありますか?
-
基本的な支援内容は変わりませんが、手帳保持者向けの追加サービスや割引は利用できないことがあります。
-
就労継続支援A型の利用対象者はどのように決まりますか?
-
障害の種類や就労の困難さ、就労意欲などを踏まえ、支援計画を作成し判断されます。
-
障害者手帳の種類によって受けられる支援は変わりますか?
-
はい、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など種類によって利用できるサービスや支援内容が異なります。
まとめ

障害者手帳を活用しながら就労継続支援A型を利用することで、「働きたい」という思いを無理なく形にできます。
A型事業所は、障害や難病のある方が安心して働き、社会とつながりながら自分に合ったペースで次のステップを目指せる大切な場所です。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、新たな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
📝参考(外部)リンク
就労継続支援A型事業所(全国版)|LITALICO仕事ナビ
就労継続支援A型事業所(京都市)|はたらきまひょ
🌈“やってみたい!”を応援する場所、トライアングルへようこそ!

💡「トライアングル」ってどんなところ?
名前に込めた想い──
「トライ(Try)=挑戦」
「アングル(Angle)=見方を変える」

そして「トライアングル」が大切にしている三つの視点:
利用者さん × スタッフ × 地域社会
この“バランスの三角形”が、私たちの出発点です。
🌱“作業”ではなく、“成長”を育む場所
私たちトライアングルグループは、京都市伏見区の藤森と竹田にて、就労継続支援A型事業所を運営しています。
(※竹田事業所はA型・B型の併設事業所です)

✨あなたの「できるかも」が「できた!」に変わる
✨あなたの「好き」や「得意」を一緒に見つける
✨あなたの「挑戦したい」を何度でも応援する
そんな“自分らしく働く”ことを目指す場所です。
💪不安があっても大丈夫。あなたのペースでOK!

「やってみたいけど不安…」
「うまくいかなかったらどうしよう…」
そんな気持ち、私たちはよくわかります。
だからこそ、失敗を恐れず挑戦できる“安心できる環境”を整えました。
🛠幅広いお仕事と支援体制
あなたの“やってみたい”に合わせて、さまざまな業務をご用意!
- 軽作業
- 創作・クラフト活動
- パソコン作業(SNS代行・ブログ作成・デザイン・動画編集など幅広い作業を提供)
- 在宅ワークも対応可能!
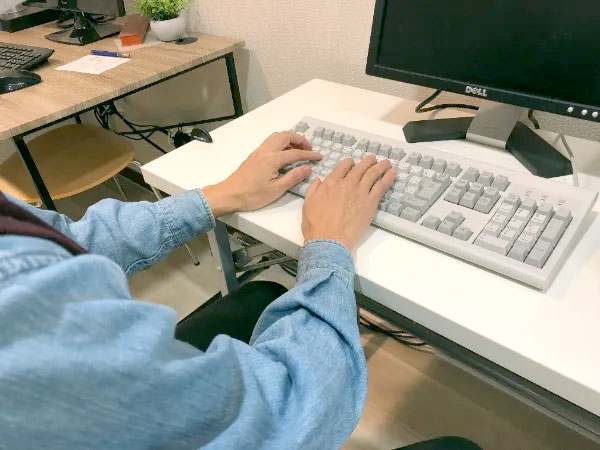
▶詳しくはこちらの「仕事の内容」もご覧ください。
就労に不安がある方も、ブランクがある方も、「挑戦したい」という気持ちがあれば、それだけで充分です。
さらに
📘資格取得支援
💼就職サポート
💬定期面談・個別相談
など、安心のサポート体制も充実!
💬まずは見学・体験からでもOK!
「ちょっと気になる」
「話だけでも聞いてみたい」
そんな方も、見学・体験を随時受付中!
あなたの“はじめの一歩”を、スタッフ一同あたたかくお迎えします。
✨あなたの未来、一緒に描いてみませんか?
「やってみたい」「挑戦してみたい」
——その前向きな気持ちこそが、すべてのはじまりです
あなたが思い描く「なりたい自分」を実現するために、トライアングルは全力で応援します。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
🏢事業所のご案内
🔹トライアングル藤森(就労継続支援A型事業所)

〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町840 セントラルプラザ1階
📞075-644-4123
🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)
アクセス:
🚶京阪本線「藤森駅」 徒歩5分
🚶JR奈良線「JR藤森駅」 徒歩20分
🚌市バス「藤ノ森」停留所 徒歩2分
🔹トライアングル竹田(就労継続支援A型・B型事業所)

〒612-8446
京都市伏見区竹田中内畑町2番地 堀田ビル3階
📞070-3272-4349
🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)
アクセス:
🚶近鉄・地下鉄「竹田駅」 徒歩8分
🚌市バス「竹田内畑町」停留所 徒歩1分
各事業所へのアクセスは「アクセス情報」をご覧ください。