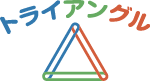就労継続支援A型の利用期間ってどうなるの?不安を解消して安心して働く方法

障害や難病があり働く方にとって、「就労継続支援A型」は心強い選択肢の一つです。
一方で
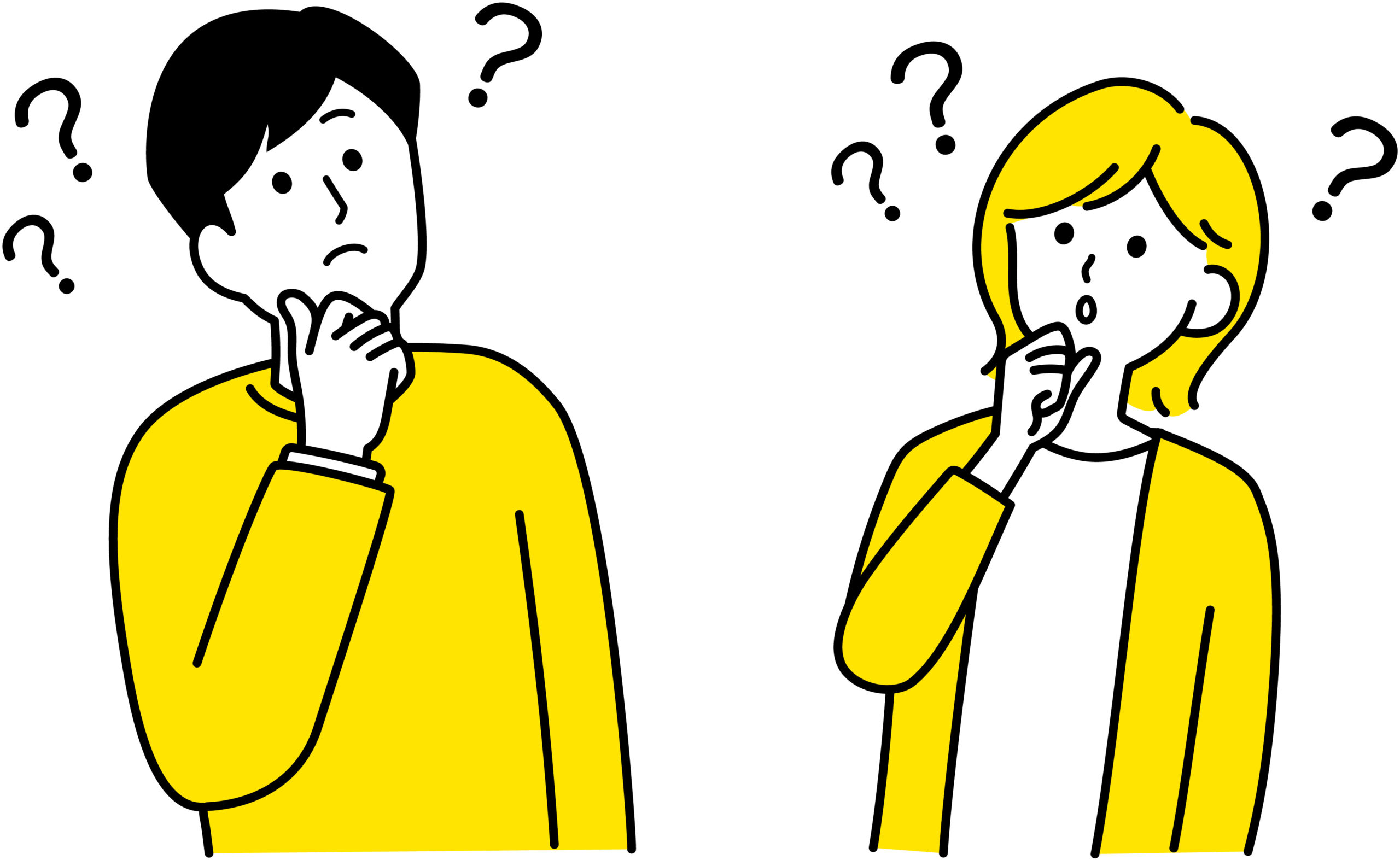
「どれくらい利用できるの?」
「期間に上限はあるの?」
といった利用期間への不安を感じる方も少なくありません。
安定した働き場所を選ぶ上で、利用期間のルールは大切なポイントです。
この記事では、A型事業所の利用期間の基本や延長方法、注意点までを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、利用期間への不安が解消され、安心してA型事業所の利用を検討する第一歩を踏み出せるはずです。
目次
- 就労継続支援A型事業所とは?
- 利用期間の上限なし!焦らずスキルアップできるA型事業所
- 利用期間に上限がない理由──A型制度の目的を知ろう
- 「利用期間の定めあり」となるケースに注意
- 気になる「更新」の仕組みと手続きの流れ
- 就労継続支援A型の「年齢制限」- 何歳から何歳まで?
- 利用期間を味方に!自分に合った将来の働き方プラン
- 🎤 就労体験の活かし方事例
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:利用期間の不安を解消し、自分に合った働き方を見つけよう
就労継続支援A型事業所とは?

まず基本として、就労継続支援A型事業所がどのような場所なのかを確認しておきましょう。
就労継続支援A型事業所とは、障害や難病のある方が、事業所と雇用契約を結んだ上で、支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。
一番のポイントは「雇用契約を結ぶ」という点です。
これにより、利用者の方は労働者として最低賃金以上の給料を受け取りながら、自身の体調や特性に合わせたサポートのもとで働くことができます。
一般企業での就労に不安がある方や、ブランクからの復帰を目指す方にとって、安定した収入と就労経験を両立できる貴重な場所と言えるでしょう。
就労継続支援A型事業所(以下A型事業所)は、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。
一般企業での就労が難しい方に対して、働く場と必要なサポートを提供し、将来的な一般就労を目指すことも可能です。
A型事業所の目的と役割
A型事業所の主な目的は、以下の通りです。
- 雇用契約を結ぶ: 利用者と事業所が雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。
- 働く機会の提供: 利用者の能力や適性に応じた仕事を提供します。
- スキルアップ支援: 職業訓練やビジネススキルの向上をサポートします。
- 一般就労への移行支援: 企業への就職活動をサポートし、定着支援も行います。
対象となる方
- 原則として18歳以上65歳未満の方
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病をお持ちの方
- 一般企業への就職が困難な方で、A型事業所での就労を通じて一般就労を目指したいという意欲のある方
📝関連記事はこちらから
就労継続支援A型とは?対象・仕事内容・利用方法・選び方まで完全解説【2025年版】
【誰が利用できる?】就労継続支援A型の対象者とその条件を徹底解説
就労継続支援A型の雇用契約完全ガイド|初心者が知っておくべき給料・条件・注意点
利用期間の上限なし!焦らずスキルアップできるA型事業所
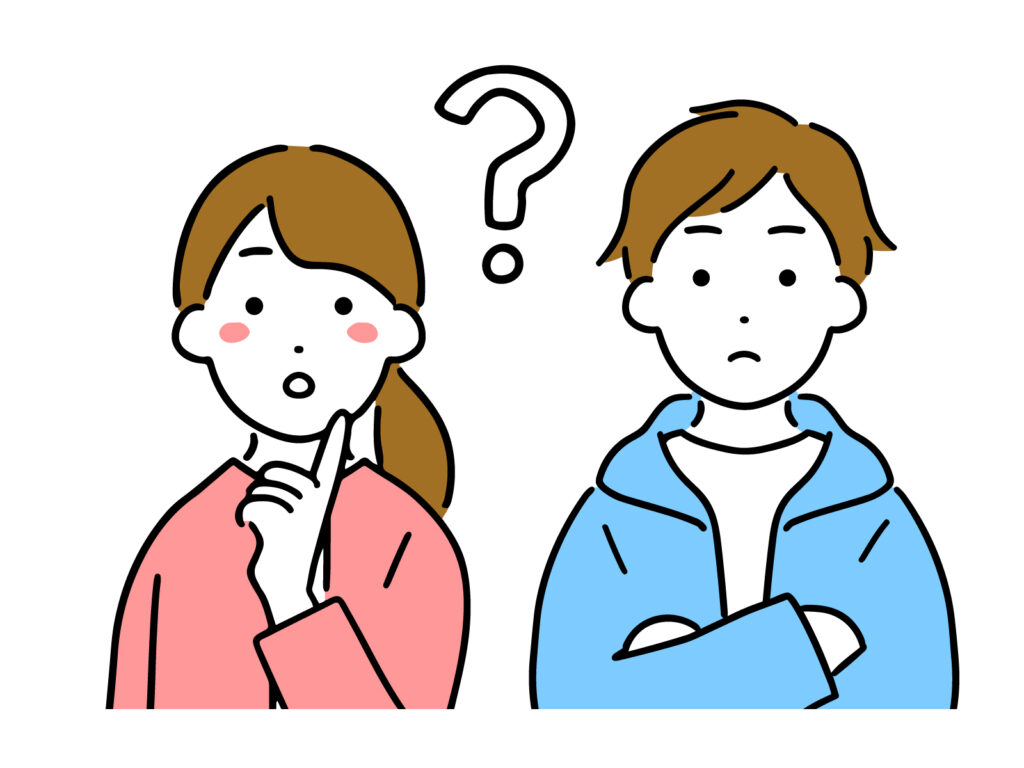
それではここから本題です。
結論から言うと、就労継続支援A型の利用期間には、法律で定められた明確な上限(「〇年まで」といった決まり)は原則としてありません。
多くの利用者の方が、自身の状況に合わせて利用されています。
利用期間が定められていないことで、利用者は焦らずに自分のペースでスキルアップや体調管理に取り組むことができます。
利用期間に上限がない理由──A型制度の目的を知ろう
A型事業所の利用期間に上限がない理由には、以下のような制度の目的があります。
- A型事業所は「一般就労を目指すためだけの準備の場」ではなく、安定して働き続けるための支援の場
- 障害や難病のある方に 安定した就労の機会 を提供することが目的
- 生産活動を通じて 知識や能力の向上 を図ることも重要な目的
- 利用者の状況やニーズに応じて 継続的な支援 を行うことができる
💡 ポイント

A型事業所は、利用者が無理なく長く働き続けられる場所としての役割も持っており、利用期間が一律に決まっているわけではありません。
「利用期間の定めあり」となるケースに注意
原則として期間の定めのないA型事業所ですが、一部例外的なケースも存在します。

ケース① 事業所との雇用契約が「有期雇用」の場合
- 多くのA型事業所では、1年ごとの契約更新で有期雇用契約を結びます
- 更新時には、利用者の目標達成度・健康状態・仕事状況などをもとに支援計画を見直します
- 契約が更新されれば利用を継続可能
ケース② 自治体独自の解釈や方針がある場合
- 市区町村によって、サービス利用に独自の方針を設けていることがあり、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口で確認すると安心です
ケース③ 一般就労への移行が明確な目標となっている場合
- 利用者と事業所で「○年後に一般就労を目指す」と具体的な目標を設定する
- 個別支援計画に沿って支援が行われる
- 目標達成をもって利用終了(卒業)となる場合があります

利用期間は決まった形があるわけではありません。
利用される方の体調や目標、事業所の考え方など、いろいろな要素をもとに決まるため、一人ひとりに合った期間になることを知っておくと安心です。
気になる「更新」の仕組みと手続きの流れ
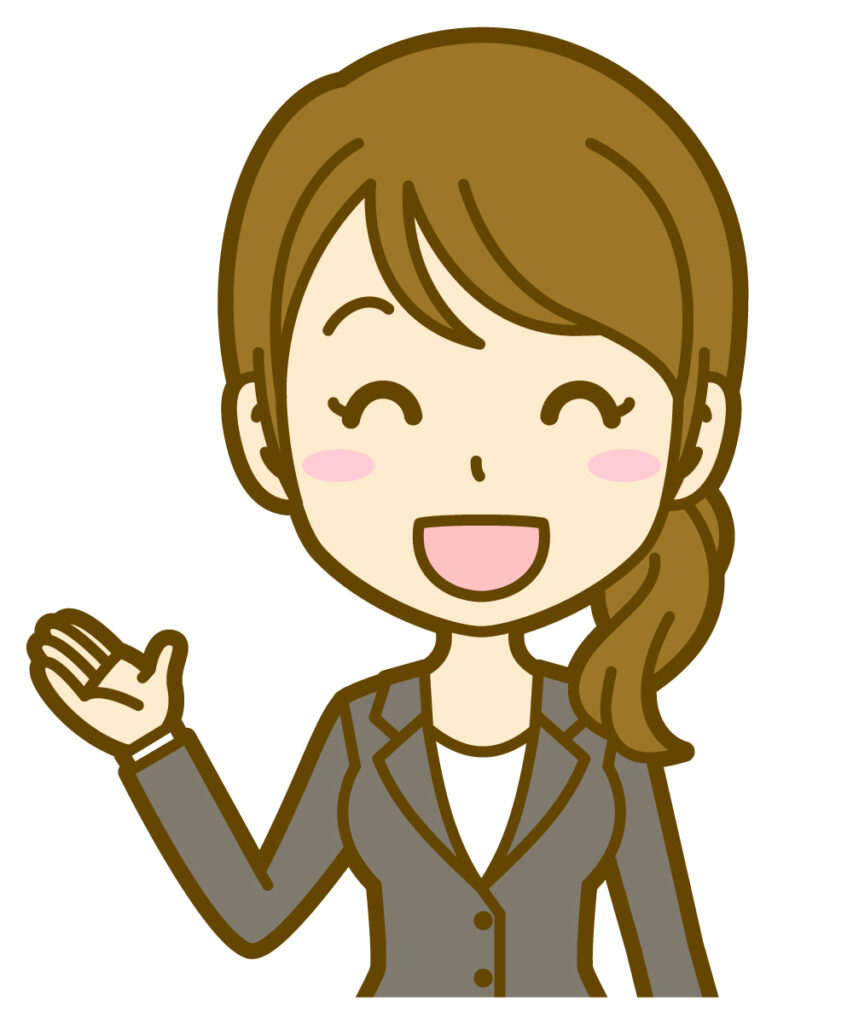
「期間の上限はない」とはいえ、多くの場合、1年ごとに利用の更新手続きが必要になります。
この「更新」はどのように行われるのでしょうか。
①更新のタイミングと「支給決定期間」
A型事業所を利用するためには、お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」を交付してもらう必要があります。
この受給者証には、サービスの利用が認められた期間として「支給決定期間」が記載されています。
多くの場合、この期間は1年間(申請した月の末日から1年後の末日まで)となっており、利用を継続するためには、この支給決定期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

📝関連記事はこちらから
【完全ガイド】就労継続支援A型を利用するには?障害福祉サービス受給者証の取得方法と注意点を徹底解説!
②更新時にチェックされる4つのポイント
更新の際には、主に以下のような点が確認されます。
主なチェックポイント
- 利用継続の意向:利用者本人が、今後もA型事業所を利用したいと考えているかどうかを確認します。
- サービスの利用状況:現在の利用頻度や、個別支援計画に沿った活動が実施できているかを確認します。
- アセスメント(評価):支援員が利用者の心身の状態や課題、目標の達成度を評価し、その結果をもとに継続支援の必要性を判断します。
- 個別支援計画の見直し:次の1年間に向けた新しい目標や支援内容について、利用者と事業所が話し合い、計画を更新します。
基本的には、利用者本人に継続の意思があり、安定して通所できていれば、更新が認められないケースはほとんどありません。
③更新されず利用終了となる可能性
一方で、以下のような場合には利用が終了となる可能性もあります。
考えられる可能性
- 一般就労への移行
本人が希望し、安定して働ける一般企業への就職が決まった場合。
これはA型事業所にとっても、利用者が次のステップへ進むことは何よりの喜びです。
- 利用者本人からの利用終了の申し出
体調の変化や引っ越しなど、自己都合で利用を辞める場合。
- 契約上の重大な違反があった場合
無断欠勤が続く、他の利用者や職員に迷惑をかける行為があるなど、雇用契約の継続が困難と判断された場合。
- 就職希望や目標
「将来的に一般企業で働きたい」「在宅でできる仕事を続けたい」など、利用者の目標に応じて支援計画が作成されます。
目標が明確であれば、期間を短く設定してステップアップを目指すことも可能です。
- 体調や通所の安定性
長期間安定して通所できるかどうかも重要な要素です。
体調に波がある場合、短期契約での利用や在宅支援を組み合わせることがあります。
- 事業所の運営方針
事業所によっては、利用者のステップアップを目的に、最長3年~5年程度の期間を目安に支援計画を組むところもあります。
就労継続支援A型の「年齢制限」- 何歳から何歳まで?

利用期間に加えて、多くの方が確認しておきたいポイントの一つが「年齢制限」です。
利用開始は「原則18歳以上」から
就労継続支援A型は、原則として18歳以上の方が対象となります。
高校を卒業した後の進路として選択する方も多くいます。
また、すでに社会経験がある方や、一度就職した後に体調や環境の変化で働き続けることが難しくなった方が、新たな働き方として利用を始めるケースも少なくありません。
利用上限は「原則65歳未満」まで
利用できる年齢の上限は、原則として65歳に達する日の前日までと定められています。
65歳になると多くの方が 介護保険制度の対象 となるため、福祉サービスの枠組みが変わることにあります。
利用期間を味方に!自分に合った将来の働き方プラン
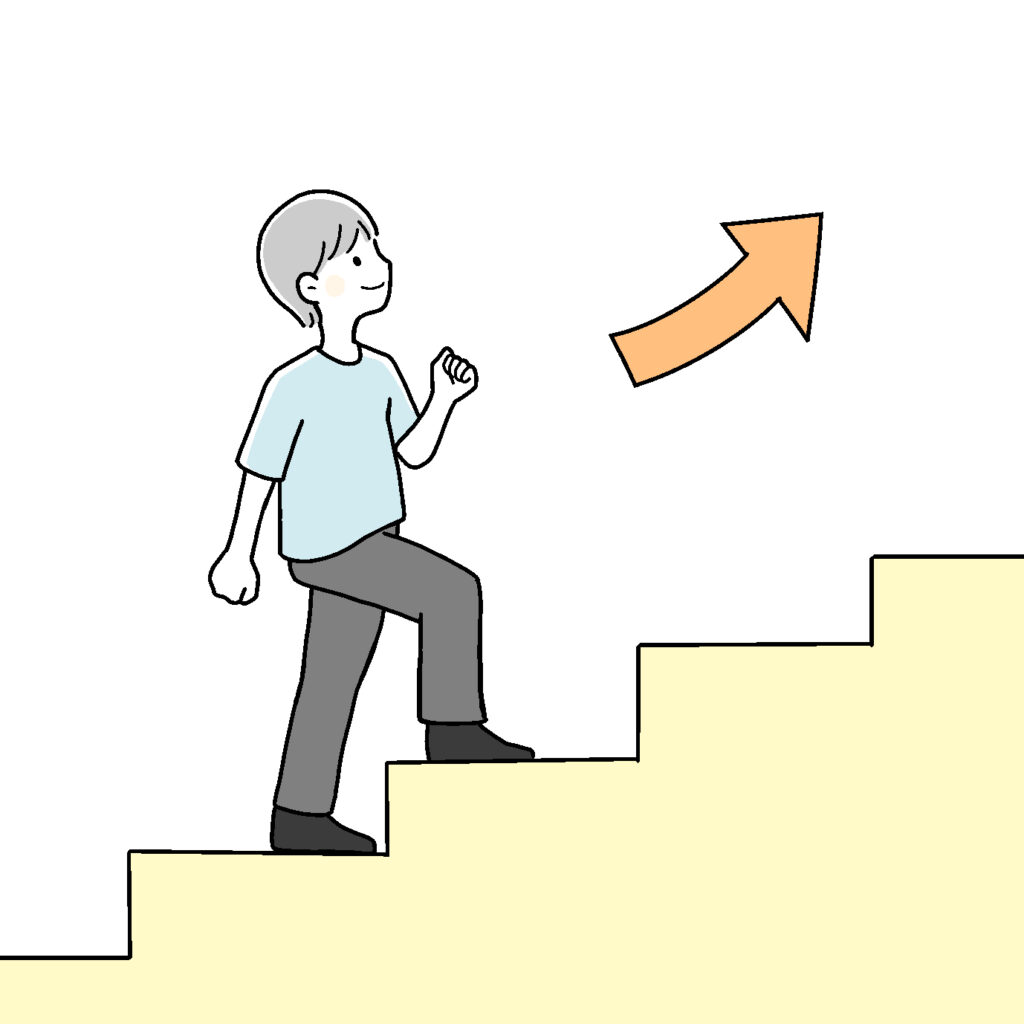
利用期間に原則的な上限がないからこそ、A型事業所をどのように活用していくか、自分なりの働き方の設計を考えることが大切になります。
- ステップ1:A型事業所で達成したい目標を明確にする
まずは、A型事業所を利用する目的をはっきりさせましょう。
・生活リズムを整えたい
・コミュニケーション能力を高めたい
・PCスキルや専門技術を身につけたい
・安定した収入を得て自立した生活を送りたい
・将来的に一般就労へステップアップしたい
など、目標が明確になるこまとで、日々の仕事へのモチベーションも高まり、支援員もあなたに合ったサポートをしやすくなります。

- ステップ2:一般就労への移行を目指すという選択肢
A型事業所での経験を通じて自信をつけ、より高い給料やキャリアアップを目指して一般企業への就職(一般就労)を目指すのも素晴らしい選択肢です。
多くのA型事業所では、一般就労に向けた支援も行っています。
・履歴書・職務経歴書の作成支援
・面接トレーニング
・ハローワークへの同行
・就職後の定着支援
など「いつかは一般就労へ」と考えている方は、こうしたサポート体制が充実している事業所を選ぶのがおすすめです。
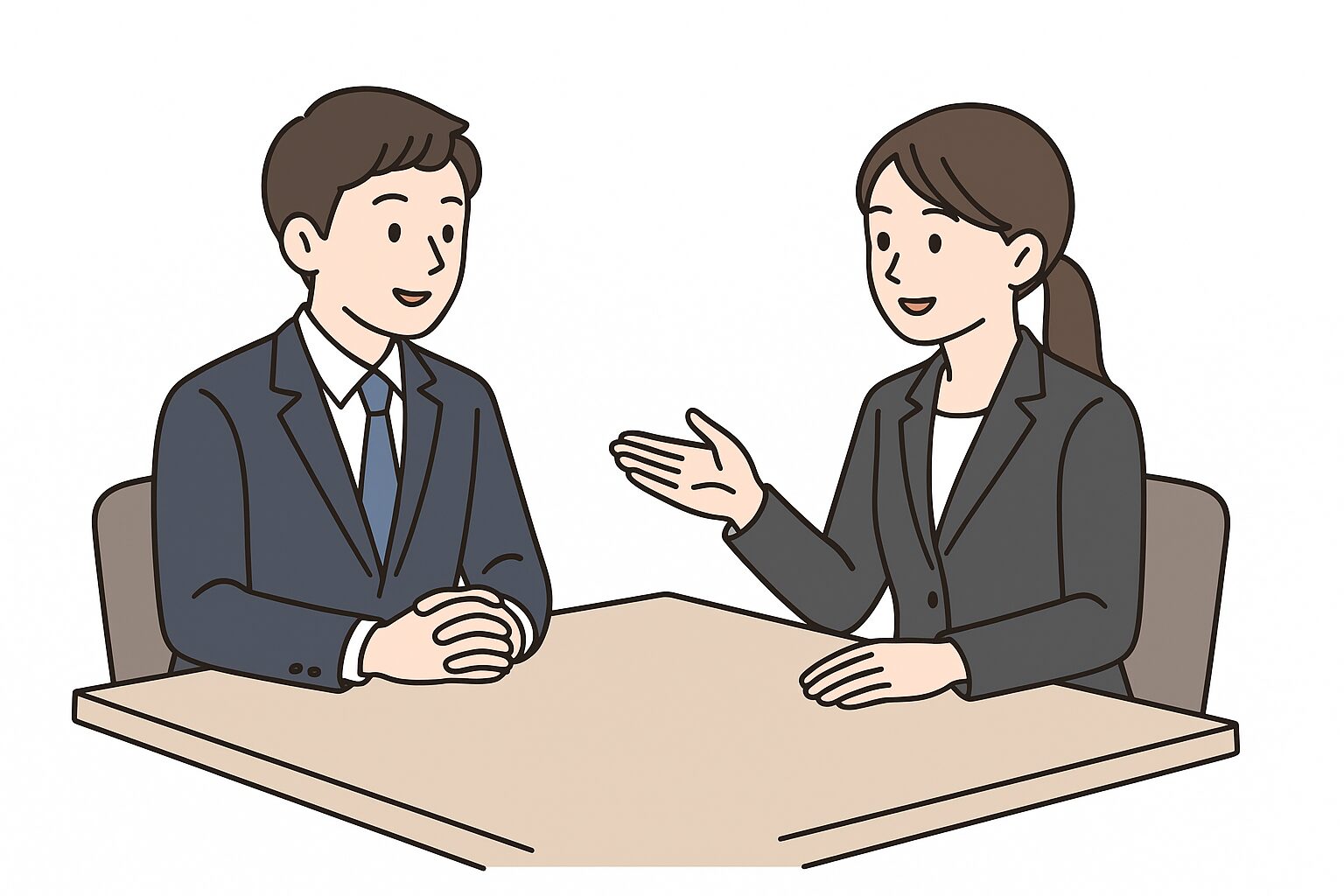
📝関連記事はこちらから
就労継続支援A型で一般就労を目指すには?必要な準備と具体的ステップを解説
【初心者向け】就労継続支援A型と就労移行支援の違いまとめ|自分に合う支援サービスの選び方
就労継続支援A型・一般就労・障害者雇用の違いをわかりやすく|あなたに合う働き方を診断!
- ステップ3:長く安心して働く選択肢としてのA型事業所
「一般就労はまだ不安」「今の環境が自分に合っている」という方は、A型事業所で長く働き続けることも有効なキャリアプランです。
無理に環境を変えるのではなく、安定して働ける場所を確保しながら、将来的に一般就労へのステップとして活かすことも可能です。
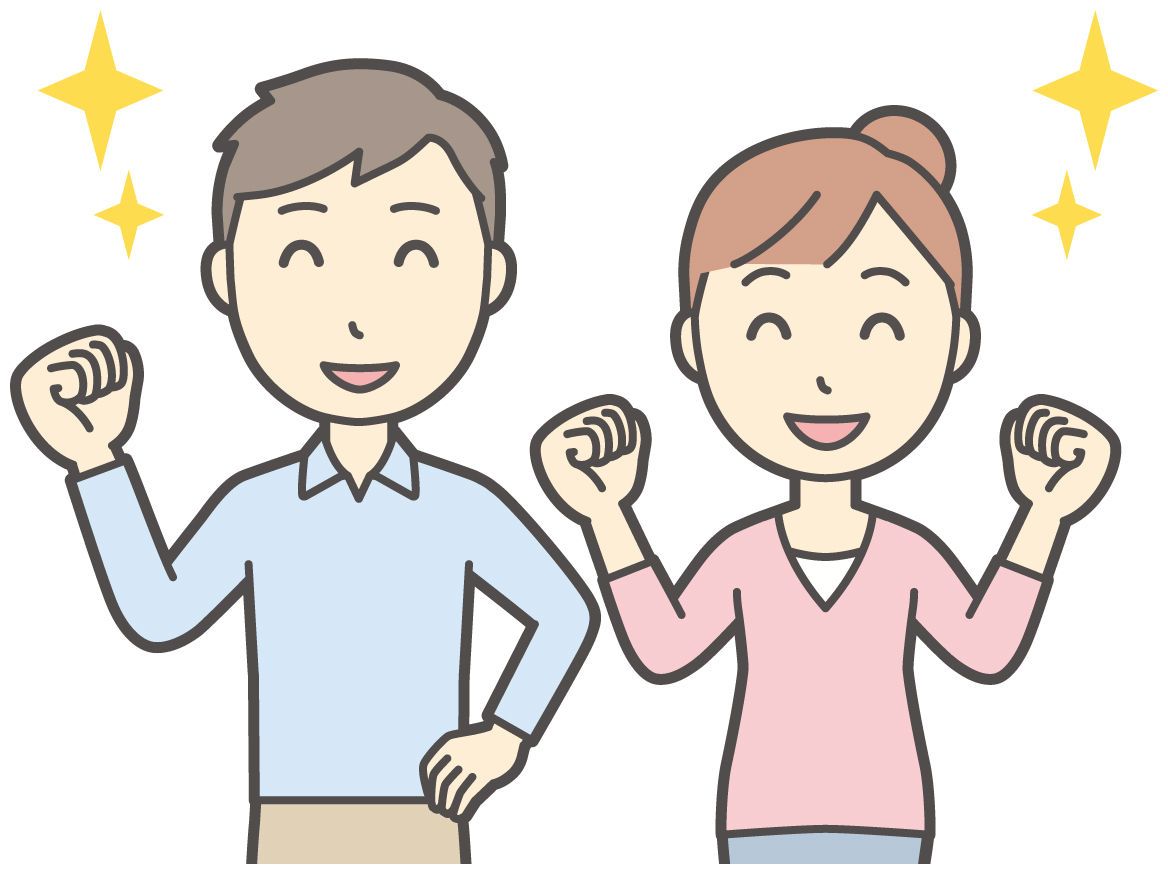
A型事業所での利用期間をうまく活用することで、一般就労へのステップアップも、長く安定して働く道も、自分らしい働き方を実現できます。
自分の目標やペースに合わせて、最適な選択を考えてみましょう。
🎤 就労体験の活かし方事例

A型事業所での就労体験は、単に働く経験を積むだけではありません。
契約期間を活用してスキルを磨いたり、得た経験を次のステップにつなげたりと、利用者の方それぞれが自分に合った形で活かしています。
ここでは、具体的な活用の事例をご紹介します。
ケース①
「初めての社会経験でしたが、丁寧に教えてもらえたので安心して働けました。事務作業のスキルも身につきました。」
— 20代・発達障害・女性
ケース②
「最初は週3日勤務でしたが、体調に合わせて少しずつ時間を増やせました。自分のペースで働けるのが安心です。」
— 30代・精神障害・女性

こうした事例からわかるように、A型事業所での就労体験は、働く力を伸ばすだけでなく、将来の選択肢を広げる大切なステップになります。
自分の目標や興味に合わせて、経験をどう活かすかを考えることがポイントです。
A型事業所を利用するまでの流れ - 安心の7ステップ

「利用してみたい」と思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、利用開始までの基本的な流れを7つのステップで解説します。
- ①情報収集・相談
お住まいの市区町村の障害福祉課や障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所で制度の説明を受け、自分に合った事業所を探します。

- ②事業所の見学・体験
気になるA型事業所を見学したり、体験利用を通じて、実際の職場環境や仕事内容を自分の目で確かめてみましょう。

- ③面接・適性確認
事業所で面接を受け、働く意欲や体調、適性などを確認します。
面接に合格すれば次のステップに進みます。

- ④障害福祉サービス受給者証の申請
面接通過後、障害者手帳や医師の診断書を用意し、市区町村の福祉課などに障害福祉サービス受給者証の申請を行います。
障害福祉サービス受給者証を申請するには、サービス等利用計画書が必要です。
相談支援専門員による作成や、ご本人やご家族が作成して申請することも可能です。
市区町村の福祉課に提出し、審査の後、受給者証が発行されます。
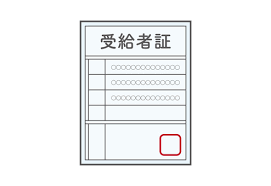
- ⑤雇用契約を結ぶ
受給者証の取得後、正式に事業所と雇用契約を結びます。契約内容や勤務条件について説明を受け、納得した上で契約を進めます。

- ⑥個別支援計画の作成
支援員と相談しながら、働き方や支援内容を具体的に計画した個別支援計画を作成します。

- ⑦利用開始
支援を受けながら実際に就労を開始します。
定期的に面談や計画の見直しを行いながら、働きやすい環境づくりを進めます。

まずは事業所やお住まいの地域の相談窓口での相談をしましょう。
ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要となります。
この流れは一般的なもので、自治体や事業所によって多少異なる場合があります。
よくある質問(FAQ)
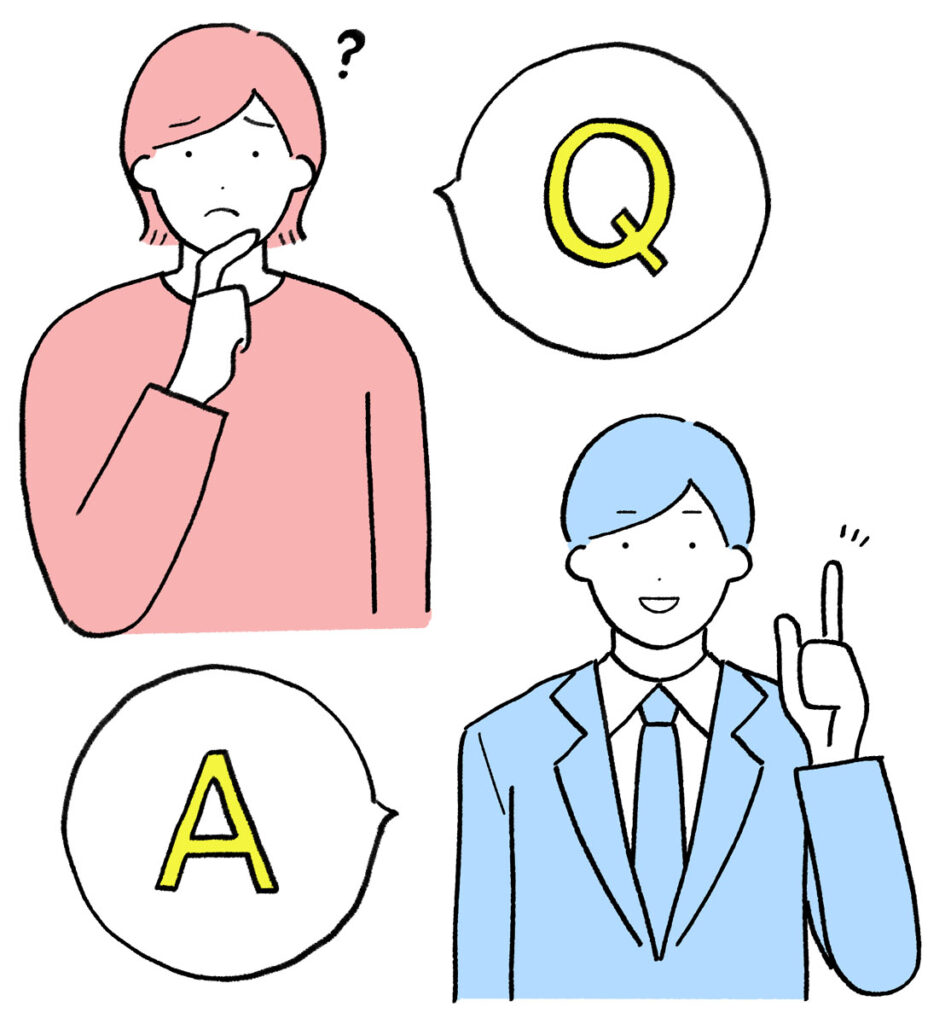
最後に、就労継続支援A型の利用期間に関してよく寄せられる質問をまとめました。
-
体調が悪くても利用は続けられる?
-
体調の波に合わせて、勤務日数や時間を調整することが可能です。無理なく働くことが前提です。
-
契約途中で退所することはできる?
-
可能です。退所する場合は事業所に相談し、必要な手続きを行います。
-
利用期間中に一般企業へ就職することはできる?
-
できます。支援計画に沿って、就職活動を進めながら利用を終了するケースも多くあります。

当事業所トライアングルでは、在宅ワークによるデザイン業務や事務作業をはじめ、一般事務職や福祉サービスの職員として一般就労へとステップアップされた方が多数いらっしゃいます。
ここでの経験を通じて実務スキルや自信を身につけ、それぞれの目標に向かって着実に前進されています。
-
B型事業所の利用期間との違いは何ですか?
-
就労継続支援B型事業所にも、A型と同様に利用期間の定めは原則ありません。 年齢制限についても、A型とほぼ同じルールが適用されます。大きな違いは、A型が「雇用契約を結ぶ」のに対し、B型は「雇用契約を結ばない」点です。
-
一度A型事業所の利用を終了した後、また再利用することは可能ですか?
-
はい、可能です。 例えば、一般就労に移行したものの、残念ながら離職してしまった場合など、再度支援が必要になった際には、改めて市区町村に申請し、支給決定を受ければA型事業所を再利用することができます。
まとめ:利用期間の不安を解消し、自分に合った働き方を見つけよう

A型事業所の利用期間は、障害の種類や就労目標、体調、事業所の方針に応じて柔軟に決められます。
大切なのは、自分の体調や希望に合った支援計画を作ることです。
制度の仕組みを理解し、事前に相談しながら進めることで、無理なく働き、自分らしい働き方や生活のスタイルを実現できます。
具体的な相談は、市区町村の障害福祉課や相談支援事業所、気になるA型事業所に問い合わせてみましょう。
📝参考リンク
・京都障害者就業・生活支援センター
就職相談・長期定着支援、ジョブコーチ支援、職場訪問などの包括的支援を行っています 。
京都障害者就業・生活支援センター/京都市障害者職場定着支援等推進センター - 京都総合福祉協会
住所:〒606-0846 京都市左京区下鴨北野々神町26番地 北山ふれあいセンター 4階
- tel : 075-702-3725
- サービス実施区域
- 京都市内担当区域(南区及び伏見区を除く9つの行政区)※但し、南区・伏見区の方のご相談にも応じることが出来ます。
・京都障害者職業相談室・ジョブパーク「はあとふるコーナー」
職業相談、職業紹介、企業実習、定着フォローなどハローワーク連携で実施。
はあとふるコーナー(はあとふるジョブカフェ)/京都府ホームページ
住所:京都市南区東九条下殿田町70(新町通九条下ル)西館3階
- 電話:075-682-8915(パーク行こ)
- ファックス:075-682-4189(良いパーク)
- Eメール:info@kyoto-jobpark.jp
📝参考(外部)リンク
就労継続支援A型事業所(全国版)|LITALICO仕事ナビ
就労継続支援A型事業所(京都市)|はたらきまひょ
🌈“やってみたい!”を応援する場所、トライアングルへようこそ!

💡「トライアングル」ってどんなところ?
名前に込めた想い──
「トライ(Try)=挑戦」
「アングル(Angle)=見方を変える」

そして「トライアングル」が大切にしている三つの視点:
利用者さん × スタッフ × 地域社会
この“バランスの三角形”が、私たちの出発点です。
🌱“作業”ではなく、“成長”を育む場所
私たちトライアングルグループは、京都市伏見区の藤森と竹田にて、就労継続支援A型事業所を運営しています。
(※竹田事業所はA型・B型の併設事業所です)

✨あなたの「できるかも」が「できた!」に変わる
✨あなたの「好き」や「得意」を一緒に見つける
✨あなたの「挑戦したい」を何度でも応援する
そんな“自分らしく働く”ことを目指す場所です。
💪不安があっても大丈夫。あなたのペースでOK!

「やってみたいけど不安…」
「うまくいかなかったらどうしよう…」
そんな気持ち、私たちはよくわかります。
だからこそ、失敗を恐れず挑戦できる“安心できる環境”を整えました。
🛠幅広いお仕事と支援体制
あなたの“やってみたい”に合わせて、さまざまな業務をご用意!
- 軽作業
- 創作・クラフト活動
- パソコン作業(SNS代行・ブログ作成・デザイン・動画編集など幅広い作業を提供)
- 在宅ワークも対応可能!
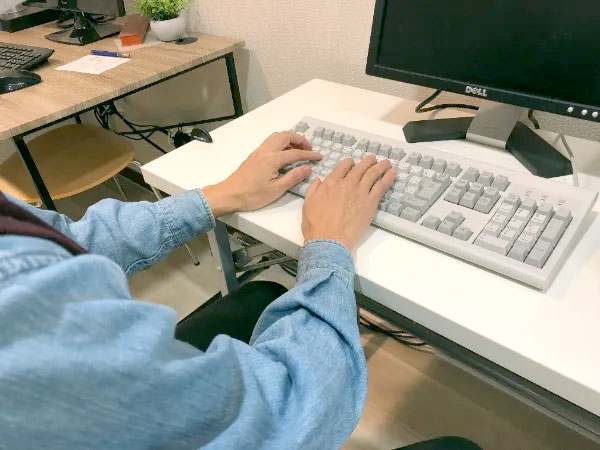
▶詳しくはこちらの「仕事の内容」もご覧ください。
就労に不安がある方も、ブランクがある方も、「挑戦したい」という気持ちがあれば、それだけで充分です。
さらに
📘資格取得支援
💼就職サポート
💬定期面談・個別相談
など、安心のサポート体制も充実!
💬まずは見学・体験からでもOK!
「ちょっと気になる」
「話だけでも聞いてみたい」
そんな方も、見学・体験を随時受付中!
あなたの“はじめの一歩”を、スタッフ一同あたたかくお迎えします。
✨あなたの未来、一緒に描いてみませんか?
「やってみたい」「挑戦してみたい」
——その前向きな気持ちこそが、すべてのはじまりです
あなたが思い描く「なりたい自分」を実現するために、トライアングルは全力で応援します。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
🏢事業所のご案内
🔹トライアングル藤森(就労継続支援A型事業所)

〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町840 セントラルプラザ1階
📞075-644-4123
🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)
アクセス:
🚶京阪本線「藤森駅」 徒歩5分
🚶JR奈良線「JR藤森駅」 徒歩20分
🚌市バス「藤ノ森」停留所 徒歩2分
🔹トライアングル竹田(就労継続支援A型・B型事業所)

〒612-8446
京都市伏見区竹田中内畑町2番地 堀田ビル3階
📞070-3272-4349
🕘受付時間:9:00~18:00(土日休)
アクセス:
🚶近鉄・地下鉄「竹田駅」 徒歩8分
🚌市バス「竹田内畑町」停留所 徒歩1分
各事業所へのアクセスは「アクセス情報」をご覧ください。